
感受性が強いって自慢じゃない。人生で勝つのは鈍感力
やや昭和の時代の響きがする「感受性が強い」って言葉。 よく聞く割に、それってどういう意味?って聞かれても答えられなかったりする...
人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

やや昭和の時代の響きがする「感受性が強い」って言葉。 よく聞く割に、それってどういう意味?って聞かれても答えられなかったりする...

(10月の東京出張時に書いたメルマガより) 東京生まれで、都内に行ったことのない場所はない気がしていましたが、田端という駅は、...

いつも、すぐに返事が来るクライアントから、しばらく連絡がなくて、何か、考えることでもあるのかな〜と、ちょっとこちらも催促せずに、時間...

(10月、日本出張時のメルマガより) 昨日は、予報に反して、小雨がぱらついた東京。 気温はぐっと低くなったのですが、自分...
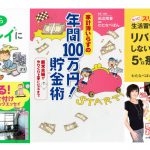
(最新版として内容を付け加え、再投稿しています。) 片づけられなかった人が、片づけが上手になる。 お金が貯められなかった...

さて、先日、容姿コンプレックスみたいなことを少し書いたのですが、機内で、まさにそれをテーマにした映画「I feel pret...

Tシャツ姿ですが、秋色の写真です。 筋トレの成果あり、上腕にいくばくかの存在感が出ていますね。 長距離ランナーはどうして...

アウトレットは、なんだか空振りでした。 簡単に行けて、施設もブランドのラインナップも素晴らしいし、駐車場もほどよく空いてて、確...

東京での食事会は、あっという間に埋まってしまったのですが、ちょうど最後のおひとり、というときに、昨日、アラフォー女性とのセッションが...

このところの相談で多いのは、パートナーシップのこと。 私も、まさかの24年間、同じ人と暮らし続ける、ということを成し遂げてしま...