
縁起でもないときのために淡々と準備できる人、しない人
今日は、月イチのトレーダージョーズへの買い出しに行ってみましたが、 NYやLAとは違い、ど真ん中のテキサスは、 厳しい態勢が...
人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

今日は、月イチのトレーダージョーズへの買い出しに行ってみましたが、 NYやLAとは違い、ど真ん中のテキサスは、 厳しい態勢が...

皆様にアナウンスしたいことが、いくつもあるのですが、 なんだか、わさわさしまくって、考えがうまくまとまりません。 宿題、課題...

春から副業を始めようというクライアントとのセッションで、 あれこれ、参考になりそうな私の体験談やら、 次にやるべきことを、い...

<3月5日時点でメルマガ配信した内容です。> 日本行きのチケットを勇ましく購入した瞬間、 複数の人から、「日本も入国制限され...

友人で、長年のクライアントで、 信頼するビジネスコンサルタントでもある戸田輝さん。 いつも大盛況のワイン会を月に10本とか開...
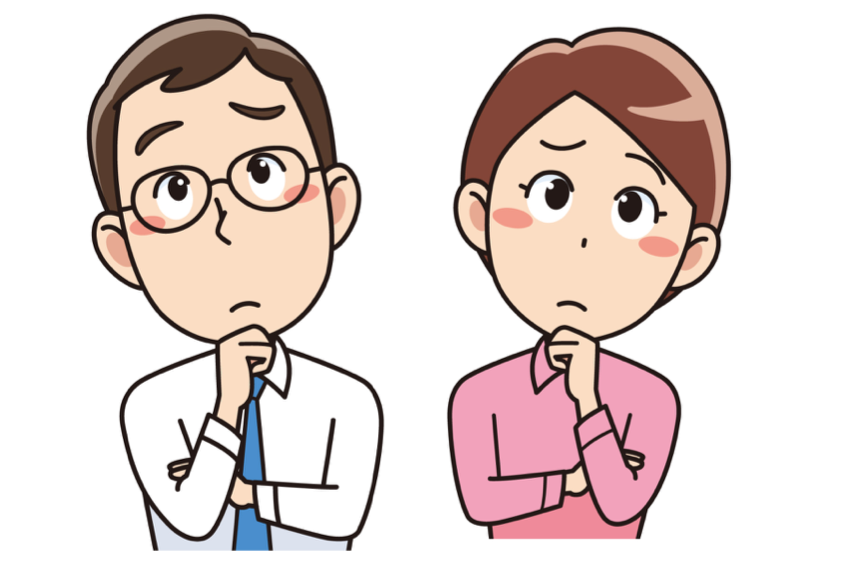
先日、【中高年、踏んだり蹴ったり】というメルマガを出しましたが、 タイトル見て、「あ、これ、私関係ないわ」と思ったのか、 開...

まあ、こういう事態を「有事」というのでしょうね。 有事(ゆうじ)とは、国家や企業の危機管理において 戦争や事変、武力衝突...

暗い話は聞き飽きたから、 楽しい話を読みたいですよね。 と思いつつ、犬の散歩から帰って、机に座ったら、 さっき届い...