
日本はどこへ行っても店員が多い印象。効率化が図れるビジネスは多いのかも
成田空港へ入る直前に、パスポートチェック、という儀式があります。 バスで行くと、2-3名の係の方が乗って来られて、形だけパスポートや身分証...
人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

成田空港へ入る直前に、パスポートチェック、という儀式があります。 バスで行くと、2-3名の係の方が乗って来られて、形だけパスポートや身分証...
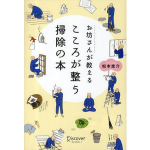
断捨離とか、ハワイ式風水に出会って以来、ずいぶんとお片づけは上手にできるようになってきたのです。 ハワイからロサンゼルスに引っ越した時点で...
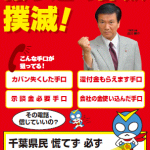
明日から日本、という状況の中で、あれもこれもと急ピッチで片付けようとしている最中、ついついマインドが日本モードになっていって、いつし...

韓国で行われているアジア大会。聞きたくないトーンのニュースも聞こえてきて、それらが事実であるのならば、本当に残念に思います。 先週の土曜に...

2014年春に公開されて、ようやく先ごろ(注:2014年9月の記事です)アメリカでDVDが発売されたドキュメンタリー映画「F...

8月後半はどっぷりハワイに浸って、戻ってから1カ月後には日本に行く予定にしていたので、この1カ月で、あれもこれもやってしまうぞー!と意気込ん...
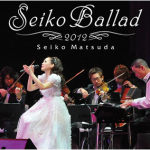
ずっと買おうかどうしようか迷っていましたが、せっかく日本に行ったのだし、と思って、やっぱり買ってしまいました。 松田聖子さんの...

ブログを始めたのが4月の下旬。アッという間に半年経ったんですね。ビックリです。 メディアの編集長として、そして社長として、10数年間のブログ...

相変わらずたくさんの嵐ファンの方がハワイコンサート情報を求めてアクセスしてくださいます。が、こちらもちょっと日本にいたり、またロサンゼルスに...
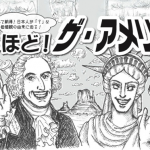
『ライトハウス』ロサンゼルス版の9月16日号が、ロサンゼルス~オレンジカウンティ界隈の日系スーパーを中心に配布されています。電子版も準備が整...