
まだ占いに頼ってるの? 自分の人生は自分でしっかり舵を取ろう
コーチングと、カウンセリングと、コンサルと、セラピーとの違いが明確にわからない方は多いようです。 確かに、それぞれを実際に使っ...
人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

コーチングと、カウンセリングと、コンサルと、セラピーとの違いが明確にわからない方は多いようです。 確かに、それぞれを実際に使っ...

年初から半年のコーチングを受けた20代男子クライアントから、泣けてくる程、嬉しいメールをいただきました。 かなり劣悪な...

スマホやパソコンに標準でついている「音声入力」の機能が、すでに実用レベルになっていることをご存じの方は、意外と少ないかもしれません。 ...

【東京在住】ヨシダケイコさん(仮名・アラフォー女性) 大手企業の商品企画スペシャリスト アラフォー女性のクライアント...

機械的な作業や、マニュアル通りにやるだけの仕事は、どんどん磨かれたAIを持ったロボットがやるようになる時代。 運転です...

「結婚しないの?」ハラスメント(笑) 最近、「結婚はしないんですか?」と聞かれることが、たまにあります。 30前後で親戚から聞か...
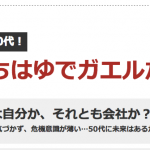
存在感と危機意識の薄い、ゆでガエルの50代です(笑)。 日経ビジネス8月8・15日号の特集「どうした50代!君たちはゆでガエルだ」...
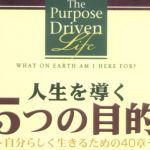
マイケル・フェルプスは自殺寸前まで追い込まれていた オリンピック史上最多のメダル数を誇るマイケル・フェルプス選手が、さらにまたメダルを...

オリンピックおたくです(笑)。 いや、正確に言うと、「でした」です。ハワイに移住する前は。 日本の放送は素晴らしいですし...

アマゾン、攻めていますね~。いいですね~。 いよいよ日本でも、図書館みたいに本がダウンロードし放題の「Kindle Unlim...