
会社を辞めるのに引き継ぎはいらない。2週間でさっぱり退社がWin-Winな理由
ご存じの方も多いと思いますが、アメリカでは、2週間ノーティス、と言って、退社の際に、2間前に届けることが通例となっています。 でも、こ...
人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

ご存じの方も多いと思いますが、アメリカでは、2週間ノーティス、と言って、退社の際に、2間前に届けることが通例となっています。 でも、こ...

先日、ロサンゼルスのダウンタウンで行われるイベントがあり、UBERに乗りました。 ダウンタウンはとにかく駐車場が不足している場...
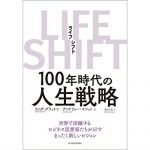
ここ数日、大好きでたまらないテーマの本を読んでいて、とてもワクワクしています。 ↓ ↓ ↓ 新しい時...

やりたいことをやれる自分になるために、セルフイメージを上げることが大事ですよ、と、よく言われますよね。 セルフイメージとは、「自分はこ...

東京駅に隣接した新丸ビルで、ネットビジネスのコンサルタントと帰国時、恒例の対面セッションの約束。 と言いつつも、気軽にドイツビ...

コーチングのセッションで最も長い時間を占めるのは、やはり「お金」を生み出すためのビジネスの話です。 「お金」」って、私たちの暮...

10月に日本出張していた間に、自宅で簡単にできる血液検査をやってみました。 去年の今頃にもやってみて、結果良好。 こんな...

(10月下旬。日本出張から終えて、すぐに出したメルマガ「未来通信」からの転載です。) 出国間際の関東地方も、27度で暖...

今年も残すところ2カ月を切りました。 なんか、ついこないだ年明けだったのに、と思ったりもするのですが(笑) その...
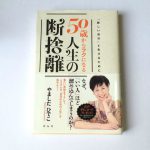
断捨離という言葉は、広く知れ渡って、ほぼ一般名称のようになってきましたが、本家本元はベストセラー「断捨離」の著者である「やましたひで...