
あなたのウエブはスマホ対応、大丈夫? 4月15日(LA)16日(OC)セミナーで徹底解説します!
最近では、スマホが普及し、ウェブサイトへのアクセスにおいて、スマホとPCの比率が半々、もしくは6割を超えはじめています。 ...
人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

最近では、スマホが普及し、ウェブサイトへのアクセスにおいて、スマホとPCの比率が半々、もしくは6割を超えはじめています。 ...
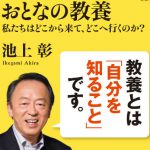
皆さんは、「あなたは教養がない人ね」と言われたことはありますか? 私はあります(笑)。 いや、笑い事じゃなく、そ...

世界に散らばるクライアントを束ねて、 Facebookの非公開グループで活発に 情報交換を行っていますが、 開設か...

毎日、終電近くまで働き続けてきた アラサー女子クライアントが、ついに 退職を決意しました。 彼女とは、去年の夏に初...

徹底ウェブ・マーケティング講座 in LA & OC 4月14日(土)・15日(日)開催! 昨年2016年6月に開催して大好...

(2014年夏の記事を改訂してアップしています。) ワークショップの一番初めの自己紹介。 最初は何だか緊張気味な...

先日、ハワイからいらした30代女性のクライアントと、家の近所のカフェで、長い時間セッションを行いました。(写真とは違う場所ですが) ...

気づけばいつも「女子」の中にいた 大学は文学部だったので、女子学生がたくさんいました。 就職した海外向け広告制作会社は、13名の社員...

クライアントさんとの信頼関係が深まってきた頃に、不意に出てきたりするのが、「虐待」についての告白です。 ご主人のことだったり、親の...

あれがない、これがない、と、 「ない」に焦点を当てながら、 未来を追いかけても、なかなか うまくいかないようです。 ...